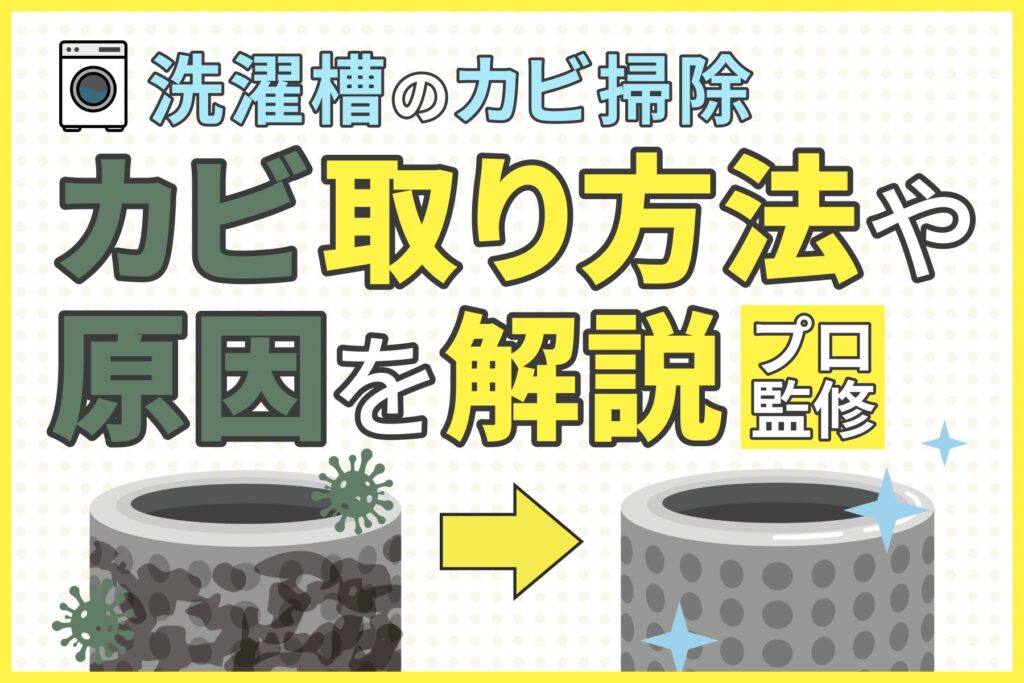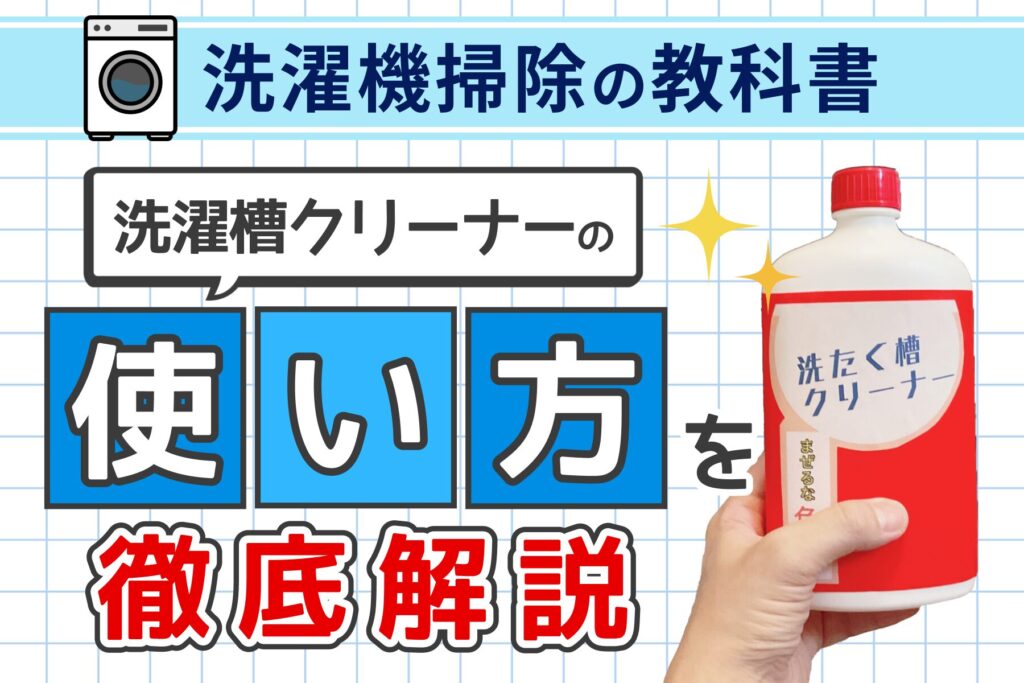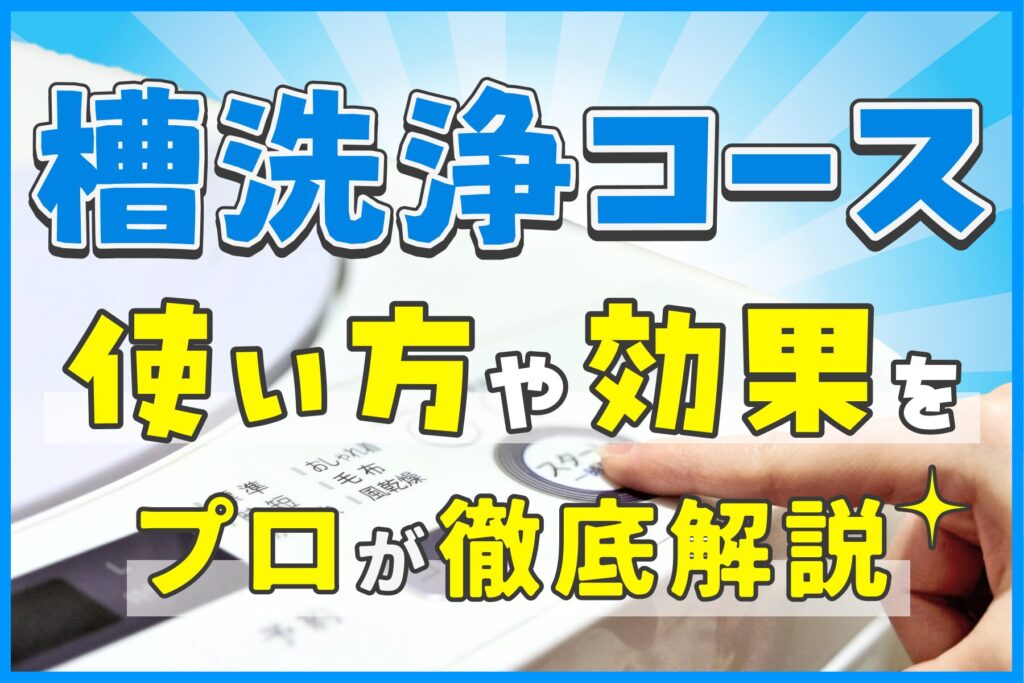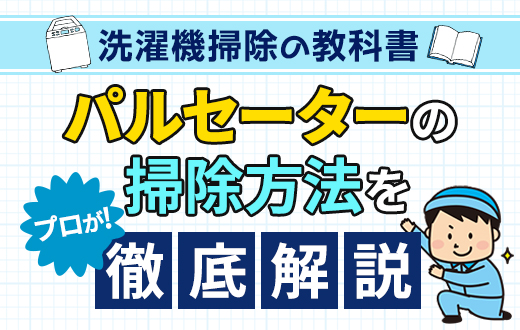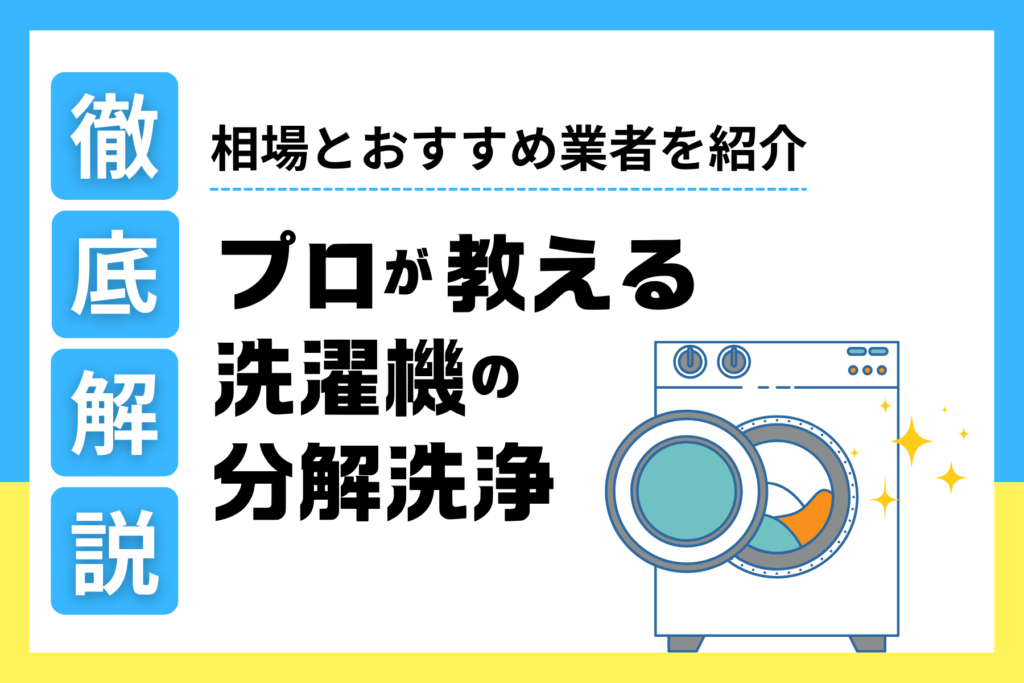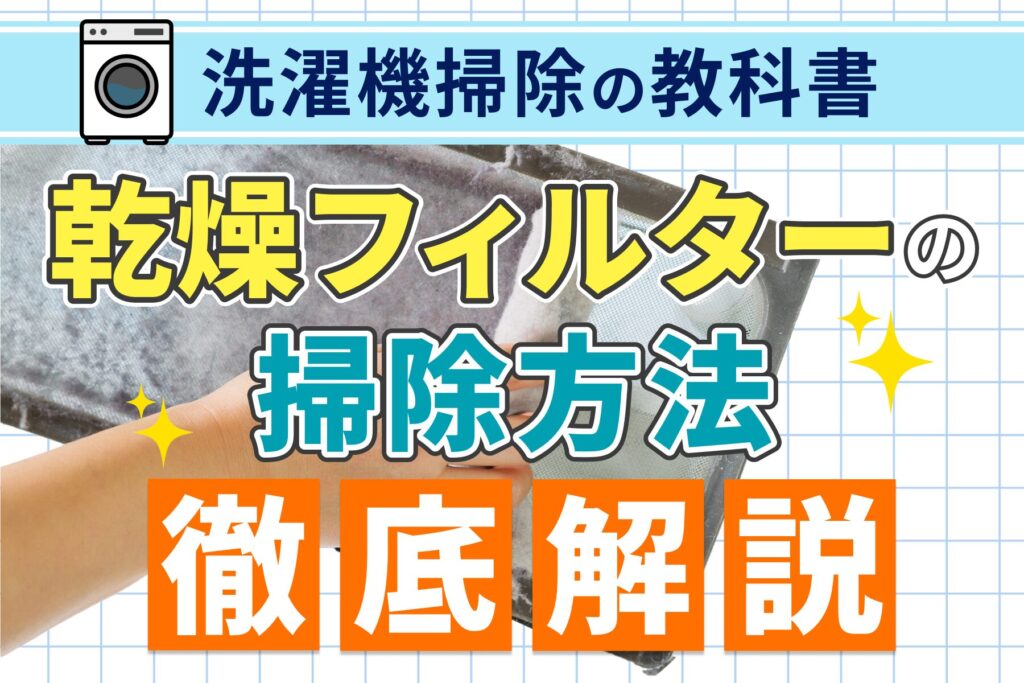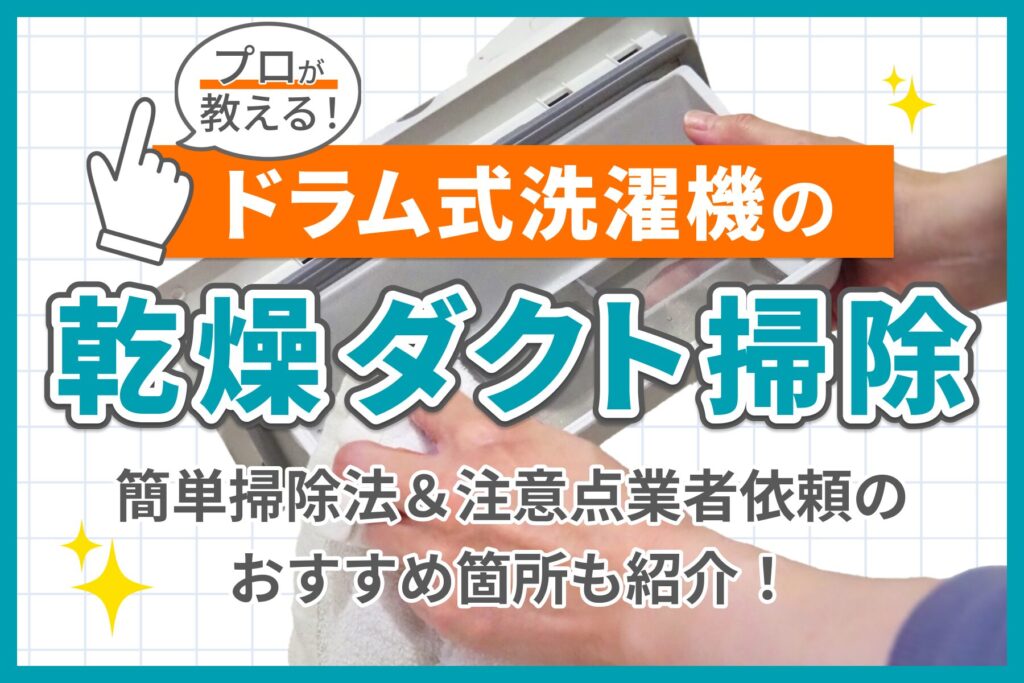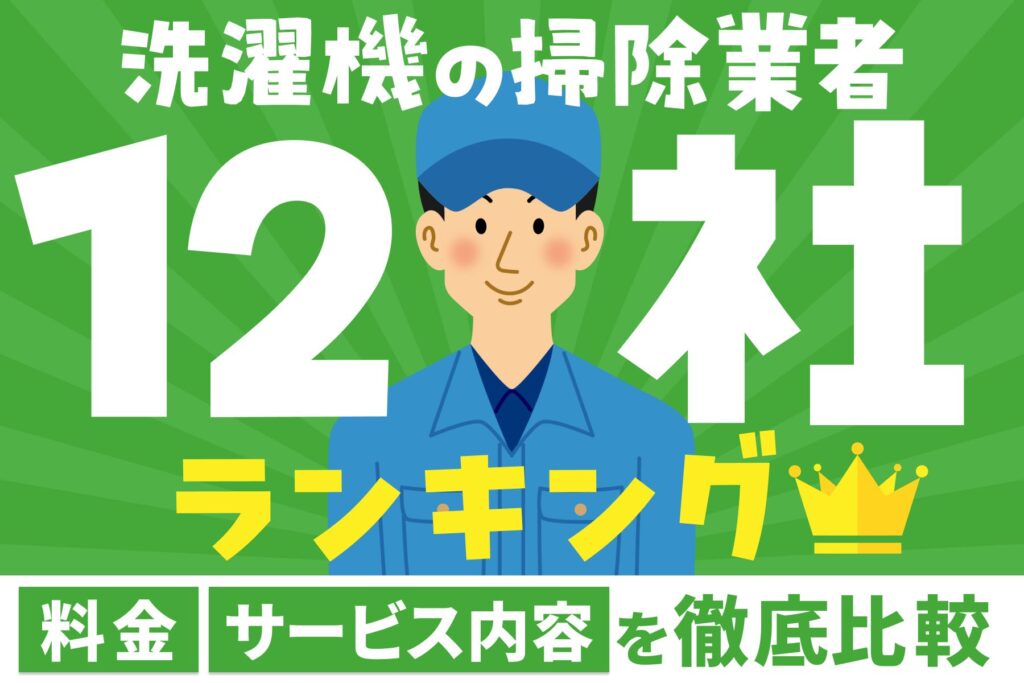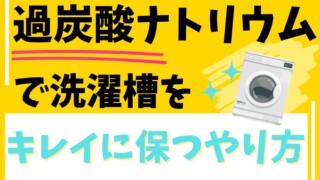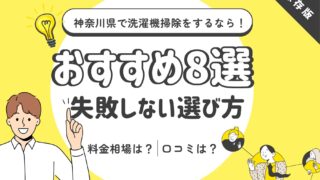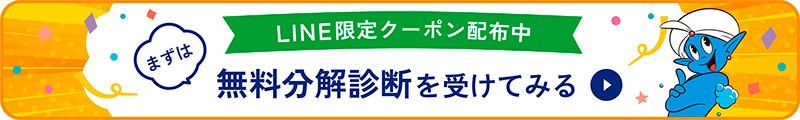【プロが解説!】洗濯物にホコリがつく3つの原因と対策
「洗ったばかりの洗濯物にホコリが付いている・・・」と悩んだ経験はありませんか?
洗濯物にホコリが付着する主な原因は、糸くずフィルターと洗濯槽の汚れ、洗濯物の繊維落ちです。
本記事では、洗濯物にホコリが付く原因から対策までを詳しく解説します。
洗濯後のホコリにわずらわしさを感じている人、解消方法を知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください!
- 1. 種類別に見る「洗濯物に付くゴミ」の正体とは
- 1.1. 白い毛羽立ったゴミ
- 1.2. 髪の毛・ペットの毛
- 1.3. 黒いカスや汚れ
- 1.4. 洗剤のかたまり
- 2. 洗濯物にホコリが付く原因
- 2.1. 糸くずフィルター
- 2.2. 洗濯槽の汚れ
- 2.3. 洗濯物の繊維落ち
- 2.4. 【ドラム式】乾燥フィルター・乾燥ダクトにホコリがたまりすぎている
- 3. 洗濯機のホコリを放置すると…?
- 3.1. 乾燥効率の低下
- 3.2. 洗濯機や洗濯物から嫌なニオイがする
- 3.3. 火災リスクにもつながります
- 4. 洗濯物のホコリを防ぐ方法
- 4.1. 糸くずフィルターのお手入れ方法
- 4.2. 洗濯機の洗浄方法
- 4.2.1. 槽洗浄
- 4.2.2. 分解洗浄
- 4.3. 洗濯ボールを使用
- 4.4. 【ドラム式】乾燥フィルター・乾燥ダクトのお手入れ
- 5. 洗濯物にホコリやゴミが付かない洗い方
- 5.1. 洗濯物の分別
- 5.2. 洗濯ネットの使用
- 5.3. 洗濯物を詰め込みすぎない
- 5.4. すすぎの回数を増やす
- 5.5. 洗剤を入れすぎない
- 6. 洗濯にホコリ・ゴミがつく原因でよくある質問
- 6.1. 洗濯するたびにゴミがつくのはなぜですか?
- 6.2. 洗濯したらホコリがつくのはなぜですか?
- 6.3. 洗濯物にくずがつく原因は何ですか?
- 6.4. 洗濯物にゴミがつかないようにするにはどうしたらいいですか?
- 7. 【豆知識】洗濯機を清潔に保つ方法
- 7.1. コインランドリーを活用!
- 7.2. 洗剤や柔軟剤を入れすぎない!
- 7.3. 洗濯物はすぐに干す!
- 7.4. 洗濯後フタを開けたままにする!
- 7.5. 週に1回は乾燥機能を使う!
- 8. 自分で掃除してもホコリがすごいときはプロの分解クリーニングも検討
- 8.1. プロの分解クリーニングを検討したいサイン
- 8.2. プロに依頼すると改善しやすいポイント
- 9. まとめ
この記事は月間500台以上の洗濯機をクリーニングしている「洗濯機のまじん」スタッフが監修しています。
洗濯機を清潔に保ち、日々の洗濯を快適にする手助けになれば幸いです。
種類別に見る「洗濯物に付くゴミ」の正体とは

洗濯後の衣類に付くゴミはどれも同じように見えるでしょう。しかし、ゴミの種類によって原因や対処方法は異なります。
- 白い毛羽立ったゴミ
- 髪の毛・ペットの毛
- 黒いカス汚れ
- 洗剤のかたまり
それぞれの特徴と予防策について、以下に詳しく解説します。
白い毛羽立ったゴミ
洗濯後の服に付く白い糸くずのようなゴミの多くは、タオルやスウェットから毛羽立ちやすい素材や繊維が抜け落ちたものです。新品のタオルやスウェットなど綿素材の衣類は製造過程で繊維が残っており、最初の洗濯で落ちる場合があります。
抜け落ちた繊維は洗濯している間に水中へと浮遊し、他の洗濯物に絡み付きます。洗濯槽の内側や排水口付近に溜まったホコリも、水流によって舞い上がり衣類に再び付きます。新品の場合は、最初の数回は単独で洗うとその後洗濯しても他の洗濯物に付きにくくなります。
髪の毛・ペットの毛
洗濯後も衣類に髪の毛やペットの毛が付着している場合、洗濯前の段階で衣類に付いていたものが、洗濯中に落ちきらず水に浮いたまま他の衣類に再付着している可能性があります。ペットを飼っているご家庭では、毛が衣類に深く絡みつくのも珍しくありません。あわせて花粉の季節は、衣類やペットの毛に花粉もつくため注意が必要です。
静電気が発生しやすい素材や、乾燥が不十分な場合にも、空気中の毛を引き寄せやすくなるため注意しましょう。
黒いカスや汚れ
洗濯物に付く黒いピロピロとしたカスは、おもに洗濯槽の裏側にこびりついた黒カビです。洗濯槽は、洗濯物と洗剤、水によって常に湿度が高くカビが繁殖しやすい環境です。
カビが洗濯機の振動や水流によって剥がれ落ちると、衣類に付着します。
黒いカスは洗剤の溶け残りや石鹸カスが原因で発生する場合もあります。
洗剤のかたまり
洗濯時に粉末洗剤を使っている場合は、洗剤が完全に溶け切らず、かたまって衣類に付着するケースがあります。水温が低い冬場や洗剤の使用量が多すぎると、粉末洗剤がうまく溶けずに衣類に付き、そのまま乾燥すると白いかたまりとして残るでしょう。
また、洗剤投入口が汚れていたり、洗剤が水分を吸って固まっていたり、ドラム式洗濯機で洗剤が直接衣類にかかったりすると、かたまりになって残る場合があります。液体洗剤であっても、柔軟剤と混ざり合ってカスが発生する場合があるため注意が必要です。
洗濯物にホコリが付く原因

洗ったばかりの洗濯物にホコリが付くおもな原因は、糸くずフィルターの問題と洗濯槽の汚れ、洗濯物の繊維落ちです。
以下で、これらの原因を詳しく解説します!
糸くずフィルター
糸くずフィルター(ゴミ取りネットとも呼ばれています)は、縦型洗濯機では洗濯槽内に、ドラム式ではドア付近に設置されています。
洗濯物から出る細かな糸くずやゴミを集める役割ですが、糸くずフィルターが汚れていると、逆に洗濯物にゴミが付着してしまいます。
糸くずフィルターは、洗濯の度に必ずお手入れをしましょう。
糸くずフィルターが破損している場合も、ホコリが洗濯物に付着します。
損傷がないか定期的に確認し、必要に応じて交換をしましょう。
洗濯槽の汚れ
洗濯機は洗濯槽と脱水槽の2重構造になっているため、隙間にカビや汚れが発生しやすいです。
隙間に蓄積されたカビや汚れが洗濯機の振動で剥がれると、ホコリになって洗濯物に付着します。
カビは皮膚炎やアレルギー反応など健康上の被害に繋がる恐れもあるため、単なるホコリよりも注意が必要です。
洗濯槽のカビについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事
参考:エステー株式会社「洗濯機のカビ汚染度に関する調査結果」について洗濯時の"洗い水"に見えないカビ汚染 洗濯機の使用年数や使用頻度とカビ汚染との相関性はなし、浜町センタービルクリニック「カビ」や「ダニ」によるアレルギー
洗濯物の繊維落ち
新品のタオルなど繊維の総量が多い洗濯物は繊維落ちしやすいです。
抜け落ちた繊維が洗濯機内の微量な汚れとくっつき、洗濯後の衣類にホコリとして付着します。
とくに新品のタオルは、素材が綿や毛羽であるため、工場での製造過程で不要な繊維やゴミ、糸くずなどが付着している場合があります。
新品のタオルなどは洗濯ネットに入れて、他の洗濯物と分けて洗濯すると効果的です!
【ドラム式】乾燥フィルター・乾燥ダクトにホコリがたまりすぎている
ドラム式洗濯乾燥機でホコリがすごいと感じる原因のひとつが、乾燥フィルターと乾燥ダクトにたまったホコリです。
乾燥運転では衣類から細かな毛羽や繊維が大量にはがれ落ち、まず乾燥フィルターに集められます。しかし、掃除が追いつかず目詰まりすると、ホコリが乾燥ダクト側へ流れ込み、内部に蓄積しやすくなります。乾燥ダクトにホコリが溜まると、温風の流れが悪くなって乾燥中に舞い上がったホコリが衣類に戻りやすくなるため、乾燥したのにホコリが増えたと感じる原因になります。
乾燥フィルターや乾燥ダクトのホコリ詰まりが進むと、乾燥効率の低下だけでなく、エラー表示や異音の原因になる場合もあります。
洗濯機のホコリを放置すると…?
洗濯機まわりのホコリは、見た目が気になるだけと思われがちですが、放置すると洗濯機の性能低下やトラブルの原因になりやすい汚れです。とくにドラム式洗濯乾燥機では、乾燥機能を使うほどホコリが溜まりやすくなります。
ここでは、ホコリをそのままにした場合に起こりやすい代表的な影響を紹介します。
乾燥効率の低下
洗濯機の乾燥フィルターや乾燥経路にホコリが溜まると、風の通り道が狭くなり、温かい風がうまく循環しなくなります。
結果として乾燥時間が長くなったり、仕上がりがいつもより水分を含んでいたり…と乾きにくさが目立つようになります。
乾燥時間が延びた分だけ電気代もかさみます。
タイマー表示よりも明らかに仕上がりが遅い、設定時間内に乾かないと感じる場合は、乾燥フィルターや排水フィルターにホコリが詰まっていないか、一度しっかり確認してみましょう。
洗濯機や洗濯物から嫌なニオイがする
洗濯機の内部にホコリがたまると、湿気と混ざり合い、カビや雑菌が繁殖しやすくなります。
とくにドラム式洗濯機では、乾燥フィルターや乾燥ダクト、排水フィルターに残ったホコリが湿気を含むと、ニオイの原因菌が増えやすくなります。
洗濯機にホコリがたまった状態で洗ったり乾燥したりすると、洗濯機全体から嫌なニオイがしやすくなり、洗い上がりの衣類にもニオイが移ってしまう場合があります。
とくに黒いカス汚れ(洗濯槽のカビ)が一緒に舞い上がると、衣類に付いたホコリと混ざってさらにニオイが強くなる場合もあります。
火災リスクにもつながります
ホコリは繊維や皮脂汚れが混ざった燃えやすい汚れです。
乾燥機能によって高温の空気が流れるドラム式洗濯乾燥機では、乾燥フィルターや乾燥経路にホコリが大量に溜まった状態で使い続けると、内部の温度が上がりやすくなり火災リスクが高まるおそれがあります。
とくに、油分を多く含むタオルや作業着を乾燥したあとに、そのままドラム内へ長時間放置すると、まれに自然発火につながる事例も報告されています。
乾燥終了後はできるだけ早く洗濯物を取り出し、毎回の乾燥後に乾燥フィルターのホコリを取り除いてホコリ対策と安全対策を意識しましょう。
洗濯物のホコリを防ぐ方法

糸くずフィルターのお手入れ方法
まずは基本の、糸くずフィルター(ゴミ取りネット)のお手入れ方法です。
フィルターをきちんと掃除するだけでホコリが解消できる場合もあるので、試してみてください。
糸くずフィルターお手入れ手順
- 洗濯機からフィルターを取り外し、中のゴミを捨てる
- ぬるま湯と浴室用洗剤、歯ブラシなどを使用し、フィルターを洗う
- よく乾燥させてから、洗濯機に戻す。
上記のフィルター掃除は月に1回を目安として徹底的な洗浄をおすすめします。
加えてフィルター内のゴミ取りは、洗濯の度におこないましょう!
糸くずフィルターのさらに詳しいお掃除方法は、以下の記事で解説しています。
おすすめ記事
洗濯機の洗浄方法
槽洗浄
槽洗浄とは、専用クリーナーを使用して洗濯槽のカビや汚れ、悪臭を除去する掃除方法です。
洗濯機の槽洗浄には「槽洗浄コースを使用しないでおこなう方法」と、「洗濯機のパネルにある槽洗浄コースでおこなう方法」の2通りがあります。
槽洗浄は月に1回の掃除頻度を目安にしましょう。
槽洗浄コースを使用しない方法
- 塩素系の洗濯槽クリーナーを空の洗濯機に入れる
- ぬるま湯を洗濯機の9割くらいまでの高さまで入れる
- 洗濯機の「標準コース」(洗い→すすぎ→脱水)で運転する
槽洗浄コースを使用しない「槽洗浄」の詳細手順は、下記の記事で解説してます。
あわせて読みたい
洗濯機のパネルにある槽洗浄コースでおこなう方法
- 塩素系の洗濯槽クリーナーを空の洗濯機に入れる
- 洗濯機の「槽洗浄コース」で運転する
- すすぎ洗いを行い脱水をする
洗濯機のパネルについている「槽洗浄コース」の詳細手順は、以下の記事で解説してます。
あわせて読みたい
また、洗濯槽クリーナーは塩素系がおすすめです。
短時間で効果も高いため、詳しく知りたい人は下記の記事で解説しておりますので参考にしてください。
おすすめ記事
分解洗浄
上記の槽洗浄をおこなっても、洗濯機内部の汚れをすべて除去するには限界があります。
洗濯機を根こそぎ綺麗にするためには、分解洗浄が必要です。
年に1回程度の頻度で徹底的な分解洗浄をおすすめします。
- 電源をOFFにし、蛇口を閉める
- 洗濯機のフタ、パルセーター、脱水槽を取り外す
- 分解したパーツを洗浄する
- パーツを乾燥させ元に戻す
パルセーターと洗濯機の分解洗浄については、こちらの記事がおすすめです↓
おすすめ記事
洗濯ボールを使用
洗濯ボールをご存じですか?洗濯ボールとは、洗濯機に入れて使用するもので、洗濯機内で衣類と一緒に回転しながらホコリや髪の毛を集めるアイテムです。
洗濯ボールにはゴムタイプとスポンジタイプがありますが、ホコリ対策にはスポンジタイプがおすすめです。
ペットを飼っているご家庭や、新品のタオルを洗濯する場合に活躍します!
【ドラム式】乾燥フィルター・乾燥ダクトのお手入れ
ドラム式洗濯乾燥機のホコリ対策で欠かせないのが、乾燥フィルターと乾燥ダクトのお手入れです。
乾燥運転中には衣類から細かな毛羽や糸くずが大量にはがれ落ち、まず乾燥フィルターに集まります。掃除が追いつかないとフィルターが目詰まりし、乾燥ダクト側へホコリが流れ込みやすくなります。
乾燥ダクトにホコリが溜まると、乾燥効率の低下だけでなく、温度が上がりやすくなり火災リスクにもつながるため、こまめなお手入れを意識しましょう。
あわせて読みたい
洗濯物にホコリやゴミが付かない洗い方

ホコリがつかないように洗濯するには、日頃の工夫が重要です。ここでは、家庭で手軽にできる洗い方のコツをご紹介します。
洗濯物の分別
繊維の異なる生地を一緒に洗うと、毛羽立ちや摩擦によってホコリが発生しやすくなります。タオルやフリースなど毛羽が出やすい素材は、綿シャツや化繊素材と分けて洗いましょう。
色物の生地から出た細かい繊維が白い生地に付くのを防ぐためにも、色物と白物を分けて洗う習慣が大切です。デリケートな衣類や装飾のある服も分けて洗えば、摩擦による生地の損傷予防に繋がります。
洗濯ネットの使用
洗濯ネットは生地同士の摩擦から保護するだけでなく、ホコリの発生や衣類への付着をおさえる役割があります。デリケートな物だけでなく、毛羽立ちやすい衣類にも積極的に洗濯ネットを使いましょう。繊維の抜け落ちをおさえ、他の衣類への付着を防ぎます。
洗濯ネットは衣類のサイズに合わせて適切なものを選びましょう。小さすぎるとしっかり洗えず、大きすぎるとネット内で動いて摩擦が増えてしまうため注意してください。
また、細目のネットを選べば、より小さなホコリ・髪の毛の漏れ出しや他の衣類への付着を防げます。
洗濯物を詰め込みすぎない
洗濯機に衣類を詰め込みすぎると、洗剤や水が全体に行き渡らず、汚れやホコリを十分に落とせません。衣類同士の摩擦が激しくなると、繊維の抜け落ちを増加させるきっかけになります。
洗濯物の量は、洗濯槽の7〜8割程度を目安にし、衣類がスムーズに回転できるスペースを確保するように心がけましょう。洗濯量に余裕があれば、洗濯物同士の摩擦も減り、毛羽立ちを防げます。
洗濯物の詰め込みすぎは、洗剤の泡立ちが悪くなる理由となり洗剤残りにもつながるため注意しましょう。
すすぎの回数を増やす
すすぎは衣類から汚れや洗剤だけでなく、浮遊しているホコリや糸くずを洗い流す大切な工程です。すすぎの回数が少ないと、水中に漂うゴミが再付着する場合があります。
洗濯機の「すすぎ回数2回」の設定や、手動で水量を多めに設定して浮遊物を効果的に除去しましょう。とくに、汚れがひどいときや衣類の量が多いときには、念入りなすすぎをおすすめします。
すすぎの際に、泡切れの良い洗剤を選ぶことも、洗剤残りを防ぐ上で重要です。
洗剤を入れすぎない
洗剤は多く入れるほど汚れが落ちると思われがちですが、実際には逆効果になる場合があります。洗剤の量が多すぎると、十分にすすぎきれず衣類に洗剤カスが残る場合があるためです。
洗剤カスが、乾燥後に白い粉のようなゴミとして洗濯機内に残り、洗濯槽の黒カビを増やす要因となります。溶け残った洗剤が衣類に付きホコリと絡みやすくなるため、洗剤の量は必要以上に入れないように注意が必要です。
ドラム式洗濯機では洗剤残りが発生しやすいため、使用する洗剤のパッケージに記載されている適量を必ず守りましょう。柔軟剤も適量を守らないと衣類にヌルつきが残ったり、吸水性が低下したりする可能性があります。
洗濯にホコリ・ゴミがつく原因でよくある質問
ここでは、よくある質問にお答えし、疑問を解消します。
洗濯するたびにゴミがつくのはなぜですか?
洗濯のたびにゴミが付く原因は、以下の通りです。
- 洗濯槽の汚れ
- 糸くずフィルターの目詰まり
- 洗濯物の繊維の脱落
- 洗剤の溶け残り
洗濯槽の裏側には、目に見えないカビや洗剤カスが溜まっていることがあり、洗濯中に剥がれ落ちて衣類に付きます。また、糸くずフィルターが詰まっていると、本来キャッチすべきゴミが水中に流れ出てしまい、衣類に再付着します。
洗濯したらホコリがつくのはなぜですか?
ホコリが付く理由の多くは、布の繊維やフィルターの汚れによるものです。衣類から出た糸くずや空気中のホコリが衣類に再び付きます。新しいタオルやフリース素材、毛足の長い衣類などは糸くずが抜け落ちやすく、他の洗濯物に絡み付きます。
洗濯機の糸くずフィルターが目詰まりしている場合も、ホコリを十分に回収できません。ネットを使用しない場合、衣類同士の摩擦が増加し、ホコリが付きやすくなるでしょう。
乾燥機能を使用する際も、乾燥フィルターの掃除が不足していると、ホコリが再び付く場合があります。
洗濯物にくずがつく原因は何ですか?
洗濯槽の裏側や糸くずフィルターに蓄積したカビや洗剤カス、抜け落ちた糸くずなどが原因です。洗濯槽の定期的な洗浄を怠っていたり、糸くずフィルターの掃除を忘れていたりすると、くずが発生しやすくなります。
衣類同士の摩擦や、洗剤の入れすぎも理由となりかねません。乾燥機のフィルターが詰まっていると、乾燥中に出た毛羽が再び衣類に付くケースもあります。
洗濯物にゴミがつかないようにするにはどうしたらいいですか?
日々の洗濯で衣類へのゴミの付着を減らすために、以下に注意してみましょう。
- 洗濯槽の定期的な洗浄
- 洗濯物の分別とネットの活用
- 糸くずフィルターを毎回掃除
- 洗剤・柔軟剤は商品に記載された量を使用
- 洗濯機のゴムパッキンや蓋の隙間にたまったホコリの定期清掃
- 乾燥機のフィルター掃除
- 洗濯前に衣類のポケットの中身確認
さらに、洗濯ボールの使用もおすすめです。これらの対策を習慣化し、ゴミの付着を減らしましょう。
【豆知識】洗濯機を清潔に保つ方法

ここまで、洗濯物にホコリが付着する原因と対策について解説しました。
最後に、日常的に意識して洗濯機を清潔に保てる5つの豆知識を紹介します!
コインランドリーを活用!
極端に汚れた衣類や大きな布団などは、家庭用洗濯機に大きな負担をかける可能性があります。
無理に洗うと家庭用洗濯機の性能や容量を超え、十分な洗浄ができないばかりか、故障の原因になる場合もあります。
とくに汚れた衣類や大きな布団は、コインランドリーの利用をおすすめします。
洗剤や柔軟剤を入れすぎない!
洗剤や柔軟剤の過剰な使用は、洗濯機内部の汚れやカビの原因になります。
すすぎ残りが洗濯機内に蓄積して、排水不良を引き起こしたり、カビの成長を促進したりしてしまうのです。
製品の指示に従い、洗剤や柔軟剤の使用量は必要最小限に抑えましょう!
洗濯物はすぐに干す!
洗濯機内に洗濯物を放置すると湿気がたまり、カビや悪臭を引き起こします。
洗濯が終わったら、できるだけ早く洗濯物を取り出して干すようにしましょう。
洗濯後フタを開けたままにする!
洗濯後の洗濯機は思っている以上に湿気が豊富で、湿気は言わずもがなカビや悪臭の原因となります。
洗濯後は洗濯機のフタを開けておき、内部を乾燥させると良いでしょう。
週に1回は乾燥機能を使う!
乾燥機能を定期的に使用すると、洗濯機内部の湿気を除去できます。
週に1回を目安に、乾燥機能のみで運転して洗濯機内の湿気を取り除きましょう!
とくに梅雨時期のような湿気が高い季節には効果的です。
自分で掃除してもホコリがすごいときはプロの分解クリーニングも検討

洗濯機を自分で掃除してもホコリが減らないときは、洗濯機内部の見えない部分に汚れやホコリがたまっている可能性があります。
こまめにお手入れをしても変わらず出てくるホコリに悩んだ時には、プロの洗濯機クリーニングを検討しましょう。
プロの分解クリーニングを検討したいサイン
ご自宅の洗濯機で以下の症状が複数当てはまる場合は、内部の乾燥ダクト・配管・洗濯槽裏にホコリやカビが溜まっている可能性があります。
プロの洗濯機分解洗浄を検討しましょう。
枠線ブロックサンプル
- 乾燥フィルターや排水フィルターを掃除しても、毎回ホコリが大量につく
- 乾燥時間が購入当初より大幅に長くなり、設定時間で乾かない
- 槽洗浄をしても黒いカスやニオイがすぐに戻ってくる
- 運転中に「ゴー」「カラカラ」などの異音が増えてきた
- 使用年数が5〜7年以上経過し、一度も内部クリーニングをしたことがない
プロに依頼すると改善しやすいポイント
プロの洗濯機分解クリーニングでは、家庭では触れられない乾燥ダクト内部や洗濯槽の裏側
、ヒートポンプ周辺、排水経路などの奥深い汚れまで丁寧にすみずみまで洗浄できます。
内部のホコリやカビを一度リセットすれば、ホコリの再付着が大幅に減るほか、乾燥時間が短縮される、洗濯物のニオイが改善する、電気代のムダが減るなどのうれしい効果も期待ができます。
洗濯機の性能を長く保ちたい場合や、何をしても改善しないときは、プロの力を一度かりてみるのがおすすめです。
おすすめ記事
まとめ
洗濯物に付くホコリやゴミは、糸くずフィルターや洗濯槽の汚れ、洗濯物の繊維落ちにくわえ、ドラム式なら乾燥フィルター・乾燥ダクトのホコリ詰まりなど、いくつかの原因が重なって発生します。
この記事では、ゴミの種類ごとの正体と対処法、ホコリを減らす洗い方のコツ、洗濯機を清潔に保つための習慣まで幅広く紹介しました。
毎日の洗濯でフィルター掃除や槽洗浄、洗剤量の見直しを少し意識するだけでも、ホコリやニオイの悩みはぐっと減らせます。
どんなに洗濯機掃除をしてもホコリがすぐに戻ってしまう、乾燥時間やニオイのトラブルが続くときは、無理をせずプロの洗濯機クリーニングも検討してみてください。内部までしっかりリセットできて、洗濯機本来の性能を取り戻し、毎日の洗濯がぐっと快適になりますよ。
おすすめの洗濯機クリーニング業者

洗濯機は構造が複雑な家電であり、クリーニングには高度な技術と専門的な知識が求められます。
そのため経験豊富な専門業者に依頼すれば、安心して質の高いサービスを受けられます。
当サイト「洗濯機のまじん」は、業界初の洗濯機クリーニング専門会社としてスタートし、分解洗浄に特化してきたプロフェッショナル集団です。

いままで関東地域対応件数No.1、そしてお客様満足度は96%の高評価をいただいています。
対応エリアも広く、東京・神奈川・埼玉・千葉などの関東をはじめ、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀などの関西、さらに名古屋を中心とした東海地域にも展開中。
| 関東エリア | 東京・神奈川・埼玉・千葉 |
| 東海エリア | 愛知・岐阜(一部エリアのみ対応不可)と三重(一部エリアのみ対応不可) |
| 関西エリア | 大阪・兵庫・奈良・京都(一部エリアのみ対応不可)・和歌山(一部エリアのみ対応不可)・滋賀(一部エリアのみ対応不可) |
出張費や駐車料金は無料ですので、安心してご依頼いただけます。

料金体系も明瞭で、
- 全自動洗濯機:薬剤投入洗浄 7,700円〜/分解洗浄 19,800円〜
- ドラム式洗濯機:薬剤投入洗浄 14,300円〜/分解洗浄 29,700円〜
と、作業内容・時間ともに事前にわかるので、はじめての人でも安心です。
プロの洗濯機掃除業者の料金プランをチェック!
▼ドラム式洗濯機 分解洗浄の事例
▼洗濯機使用年数2年 縦型洗濯機 分解洗浄の事例
毎日使う洗濯機だからこそ、内部まで清潔にして快適な暮らしを。今すぐチェックして、安心・清潔な洗濯ライフを始めましょう!
あなたのご家庭の洗濯機も、プロの技術で新品同様にリフレッシュしませんか?

まずはお気軽にお問合せください。
投稿者プロフィール

- 洗濯機クリーニングのスペシャリスト。毎月50台以上の洗濯機を新品同様に蘇らせることで顧客からの絶大な信頼を築いています。単に清掃を行うだけでなく、お客様とのコミュニケーションを重視し、日々のお手入れ方法について専門的なアドバイスを提供。期待を超えるサービスで、お客様に感動と笑顔をお届けします。
最新の投稿
 洗濯機の掃除2024年12月9日洗濯機掃除用スプレーおすすめ3選!使い方や効果を解説
洗濯機の掃除2024年12月9日洗濯機掃除用スプレーおすすめ3選!使い方や効果を解説 洗濯機の掃除2024年12月2日過炭酸ナトリウムで洗濯槽をキレイに保つやり方や注意点を徹底解説
洗濯機の掃除2024年12月2日過炭酸ナトリウムで洗濯槽をキレイに保つやり方や注意点を徹底解説 洗濯機の掃除2024年11月16日全自動洗濯機の掃除は家にあるもので簡単!正しいやり方と効果が高い掃除法をプロが解説
洗濯機の掃除2024年11月16日全自動洗濯機の掃除は家にあるもので簡単!正しいやり方と効果が高い掃除法をプロが解説 洗濯機の掃除2024年11月12日神奈川県の洗濯機掃除業者おすすめ8選!料金相場や業者の選び方・口コミを紹介
洗濯機の掃除2024年11月12日神奈川県の洗濯機掃除業者おすすめ8選!料金相場や業者の選び方・口コミを紹介